業界に入ってしまうと学生時代との時間の流れ方が変わるので気が付きにくいですが、建築学生を中心に以前よりもデジタルスキルを持つ人材は増えてきています。
学生のうちからしっかりとしたスキルを身に着けて新卒即戦力なんていう事も珍しくないかもしれません。
今回は建築業界では一般的になったRhinoceros(以下、Rhino)についてのお話です。
 panna
pannaRhinoでBIMってできないのかな?という視点で、Rhinoの可能性や世界的シェアのBIMソフトAutodesk Revitとの違いを考えてみました。
BIMという言葉の認知度は上がれども、世界共通の定義はまだまだされていないのが現実。
BIM自体の捉えられ方があいまいな今だからこそ、様々な試みと共に他業界を巻き込んでいくことで建築業界が大きくなる可能性を感じています。
建築物を情報化して活用するという観点では、RhinoもBIMらしい振る舞いのできるツールだと思います。
RhinocerosでBIMってできるの?
この記事を読んでいる方はRhinoユーザー、もしくはRhinoってどんなソフトなんだろうという興味をお持ちの方だと思います。
もともとRhinoは3Dモデリングソフトという位置付けですが、Grasshopperの登場をきっかけに、建築業界で言えば意匠・構造・環境の設計者を中心としたデザインやエンジニアリングの検討に使われるようになります。
設計者自身がアルゴリズムを組み立て、設計の中で生み出されるデータをパラメトリックに扱う生産手法が、広く使われるようになりました。
パラメトリックにデータを扱うとはいえ、次のような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。
 建築業界人
建築業界人でもBIMソフトじゃないから、RhinoでBIMは無理でしょ?
誤解を恐れず言ってしまうと、RhinoでもBIMはできると考えています。
BIMはワークフローである
AutodeskはBIMについて次のように定義しています。
BIMとは、Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称で、コンピューター上に作成した3次元の建物のデジタルモデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性データを追加した建築物のデータベースを、建築の設計、施工から維持管理までのあらゆる工程で情報活用を行うためのソリューションであり、また、それにより変化する建築の新しいワークフローです。
BIMとは? | BIM Design (bim-design.com)
ここで、注目すべきキーワードは「建築物のデータベース」「情報活用」「新しいワークフロー」です。
 panna
pannaAutodeskの定義を参照し、BIMとは「建築物のデータをデータベースにため込み、その情報を取り出して活用する新しいワークフロー」だと言い換えてみます。
今ままでのやり方は、情報が色んな所に散らばっていてどのデータが最新データなのかよく分からず、整合性の管理が難しいなどの問題を抱えています。

それを、1つの保管場所「データベース」に取り出しやすい形で情報を集めて管理することで、他の用途へ活用できるようになるため、建築の生産活動全体を通じて健全で効率のよいワークフローを実現できます。

環境構築や業務の進め方の統一など時間がかかるという課題はありますが、実現後は非常に効率の良いワークフローとなります。
その中で、ワークフローを回す役割の1つとしてRhinoは力を発揮できます。
Rhino+Grasshopperの得意な事
そんな新しいワークフローの中でRhinoはどの部分を担うのでしょうか。
それは、データの作成・活用です。
 panna
pannaRhinoは0からデータを作ることもできますし、既にあるデータを使って様々な検討を行うデータ活用も得意です。
単純なワークフローの中でRhino+Grasshopperを使ってみる
基本設計段階を想定し、Rhino+Grasshopperでデータの活用をしてみましょう。
例えば【鉄筋コンクリート造の柱がどんな見え方になるのか】という検討をしてみます。
 panna
panna分かりやすさのために狭い範囲のシステム化の例を紹介しますが、建築物全体で考えても本質は変わりません。
ちなみに、基本設計段階ではLOD200程度を目指す案件が多いです。
モデルの形を決める情報(形状データ)や、持っている情報(属性情報)をどこまで細かく必要とするかの程度を、プロジェクトの進行度と合わせて管理するようなイメージを持ってください。
「この段階ではここまでの情報が必要だ」と、あらかじめみんなで共有しておくことで、何がいつまでに必要か把握しやすくなります。
LOD200程度であれば、建築物の大体の形と位置情報が必要になります。
基本設計段階での柱の見え方の検討なので、次の情報があれば検討を開始できます。
- 形状データ(幅と奥行)
- 位置情報(柱脚と柱頭の位置)
Grasshopperでこの情報をインプットデータとしたアルゴリズムを作成することで、情報が変わっても検討の繰り返しを容易に行うことができます。
太い柱の場合と細い柱の場合でどのように見え方が変わるのかという検討では、Grasshopperの中で設定している柱の形状データを変えることで即座に検討を行うことができます。
実際に下記の情報を可視化してみます。
- 形状データ:柱幅800mm, 柱奥行800mm
- 位置情報:柱脚の位置(X, Y, Z= 0,0,0),柱頭の位置(X, Y, Z= 0,0,5000)

情報だけではどんな柱かイメージできませんでしたが、Grasshopperでデータを活用することでどのような柱か把握できるようになりました。
この柱のデータ(形状や位置)は構造設計者による解析や設備機器の兼ね合いによっても変わります。
エンジニアリング検討によって作成したデータをデータベースに保存することで、そのデータをそのまま今回のような柱の検討のインプットデータとして活用できます。
そして、柱の見た目検討システムでスタディし、何か問題が起きれば前のフェーズに戻って検討します。
このように、チーム内のメンバーが常に同じ情報を使って検討を行うので、最新の情報がどれなのか管理する手間や手戻りを減らしやすくなります。
建築生産の過程で生まれる情報は、データベースに保管することでRhinoやGrasshopperなどのソフトで活用できます。
RhinoでBIMができないというわけではありません。
データの管理がもたらす利益とは
データ管理によって他のフェーズでデータの活用ができるフローが整えば、業務内容は情報の作成・更新作業に変わります。
前のフェーズで作成した情報をデータベースから取り出して現フェーズで必要な検討を続け、情報の作成と更新が完了したらそのデータを次のフェーズで活用するためにデータベースへ保存します。
その繰り返しによって整合性の問題や無駄なデータ作成のリスクを減らすことができます。
ここで重要なことは、3つあると考えています。
- 生産活動を進めるために必要な情報は何か整理して一元管理する事
- プロジェクト全体で同じ情報を活用できるようにする事
- 同じデータを使うためにビジネス全体をシステム化する事
この3つの重要事項は、AutodeskのBIM定義の中で注目すべきキーワードとして挙げた「建築物のデータベース」「情報活用」「新しいワークフロー」とリンクしています。
この重要なキーワードを達成していれば、データ作成・活用という用途でRhinoの力を発揮できます。
ツールはなんでもいい。社会全体の資産である情報に注目するべし
建築業界には様々な業務があるので、そもそも1つのソフトウェアで完結するようなワークフローである必要はありません。
情報の作成はスケッチでもデジタルツールでもどのような作られ方でもいいです。
重要なのは、ビジネスの目的を達成するために、毎日生み出されるデータの中で何が必要かを理解したワークフローになっていることです。
 panna
panna必要な情報を管理して活用するためのシステムを作りましょう。
誰でも使えるような形で情報を蓄積することができなければ、その段階でしか使えないデータになり、業界をまたいで引き継いでいけるような価値のある情報資産にはなりえません。



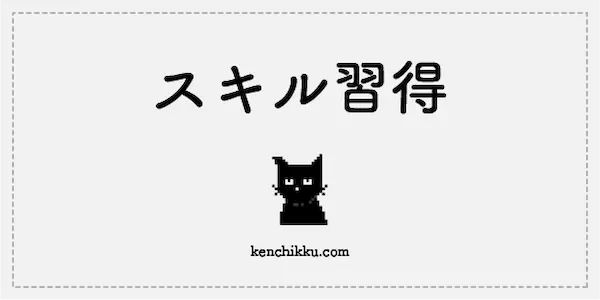
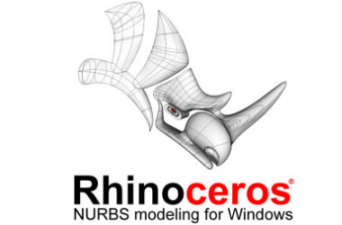
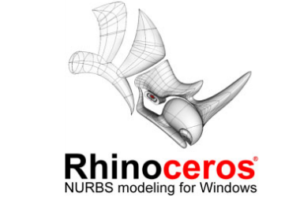

コメント